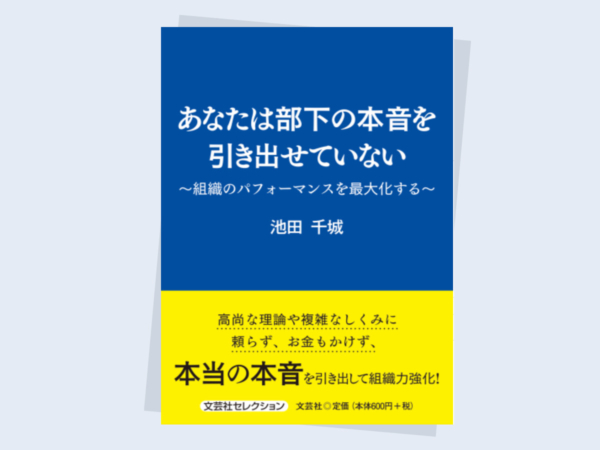経営者の愚痴
「いくら言っても社員が動かない」――そう感じたことはありませんか?
組織を変えたいと思っても、現場は思うように動かない。
その原因は“社員の意識”ではなく、“思考する環境”にあるのかもしれません。
本稿では、企業収益力向上と行動変容をテーマに、
「経営者自身が変わること」こそが、思考する組織づくりの第一歩である理由を解説します。
行動変容とは言うけれど
従業員の給与を上げ、企業としての収益力を高めたい。
それは、経営者なら誰もが抱く願いでしょう。あなたもそうではありませんか?
しかし、その実現には「高い付加価値を、最小人員で提供できる会社」に変革する必要があります。
そのためには、管理職も社員も、自らの業務に付加価値を生み出せるような仕組み、
――すなわち、能動的に“考え、動く”企業風土を築くことが欠かせません。
最近では「行動変容」という言葉をよく聞きます。
ですが、指示待ちの社員や、業務範囲に固執する体質のままでは、行動変容など望むべくもありません。
特に中小企業では、社長自らが現場業務に追われ、経営者本来の仕事――戦略立案、新規事業、トップセールスなど――に手が回らないことも多いものです。
これでは、社員の給与を上げるどころか、事業の持続的な成長さえ難しくなってしまいます。
思考しない組織は、思考できない組織になる
社員が指示待ちになるのは、“考えない”からではなく、“考えなくても仕事が回る仕組み”だからです。
思考を奪うのは社員の怠慢ではなく、環境の設計ミスなのです。
つまり多くの場合、「思考する環境」が整っていないことにあります。
では、「思考する環境」を整えるには何が必要なのか。
試しに、生成AIに意見を求めてみました。ChatGPTの答は、次の二つでした。
1)経営方針の言語化・視える化
社長の考えや中長期目標、業務方針を明文化する。
これにより、組織全体が共有できる「思考の土台」をつくる。
2)思考を社員に連鎖させる仕組みの構築
方針を業務に落とし込み、社員が立案する計画・企画をチェックする。
「計画書」や「企画書」を通じて、社長の意図が現場に根づいているかを確認する。
これが機能すれば、現場主導の体制が整い、社長は経営に集中できるようになる。
なるほど。どちらも筋の通った“正論”です。
しかし、この二つだけでは“正しく思考する環境”は完成しません。
もう一つ欠かせない要素――それは、経営者自身の行動変容です。
経営者が変わらなければ、社員が変わるはずがありません。
なぜこの問題は改善しづらいのか
/
経営者自身の「行動変容」なしに、組織は変わらない
\
それは、【従業員の行動変容の前に、経営者自身の行動変容が必要】ということ。
冒頭の愚痴――
「こうしろ」「ああしろ」「ルールを守れ」――
こうした言葉が口をつく経営者ほど、自らを変える必要があることが多いのです。
中小企業に限らず、上場企業でも同じです。
思い込みや過去の成功体験に縛られ、「○○ありき」で戦略を立ててしまう。
流行語を聞きかじって表層的に導入し、課題の本質を見誤る。
そんな経営者を、筆者は数多く見てきました。
自発的な組織へと導く考え方
「仕組み化」「DX化」「行動変容」――どれも重要なテーマです。
しかし、その前に取り組むべきは、【従業員が自発的に動ける“環境”をつくること】です。
心理学では「ナッジ理論」という考え方があります。
強制ではなく、自然に望ましい行動へと導く仕組みを指します。
経営者が「こうしろ」「ああしろ」と命じても、人は動きません。
けれども、考えざるを得ない仕組み、動きたくなる環境があれば、人は自ら行動を起こします。
例えば、焼き鳥屋さんにある、食べた後の串を入れる竹筒を思い出してみましょう。
ほんの小さな変化から
「でも、忙しくて経営者が自分を変えるなんて無理では?」
とおっしゃる方も多いでしょう。
しかしこれは、ほんの小さな変化から始められることなのです。
経営者が変われば、社員も変わる。
社員が変われば、組織が変わる。
組織が変われば、収益力も上がる。
その最初の一歩は、経営者自身の“気づき”です。
「自分はわかっている」「自分はちゃんとやっている」
。。。それはただの思い込みかもしれませんよ。
自社の「思考する環境」を点検してみませんか?
無料相談はこちらから。